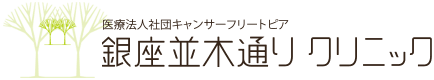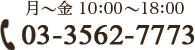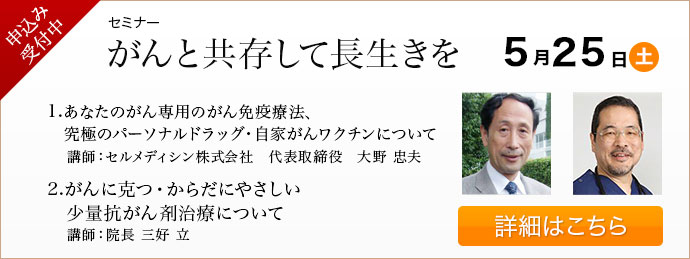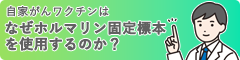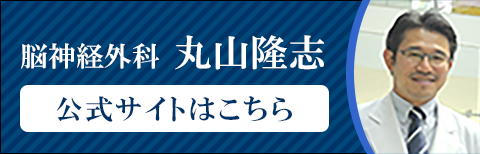がん休眠療法センター
概要
| 所在地 | 東京都中央区銀座4-2-2-7F 銀座並木通りクリニック内 |
|---|---|
| 担当医 | センター長:高橋 豊 センター長代行:三好 立 |
| 開設経緯 | 【2007年5月】 銀座並木通りクリニックで「がん休眠療法」開始 【2022年6月】 「がん休眠療法」の普及のため、銀座並木通りクリニック内に「がん休眠療法センター」を設立 「がん休眠療法」の提唱者である高橋豊医師がセンター長に就任 |
がん休眠療法センター設立目的
- 1:標準治療後あるいは標準治療が適用されなくなった患者に提供される治療を「セカンドがん治療」と位置付けする。
- 2:そのセカンドがん治療の方法論の一つである「がん休眠療法」の啓蒙活動を行い、医師・看護師をはじめとした医療従事者、患者、患者家族、がん診療に関わるすべての人々へ同療法の周知ならびにその普及を図る。
- 3:がん休眠療法に関する研究会の発足。
センター長:高橋 豊

1955年 石川県生まれ
金沢大学医学部卒 医学博士
がん休眠療法提唱者
- 元金沢大学がん研究所 腫瘍外科 教授
- 元千葉大学医学部 がん分子免疫治療学 教授
- 前国際医療福祉大学医学部大学院 臨床腫瘍学 教授
- 前日本癌学会評議員
- 日本消化器外科学会特別会員
私はこの2021年末に定年退職致しました。
医学生時代を含め、これまで45年間外科医として消化器がんと肺がんの診断と手術(金沢大学、国立がんセンター)、腫瘍医として抗がん剤治療(金沢大学、国際医療福祉大学)、基礎研究者としてがんの研究(米国テキサス大学MDアンダーソン癌研究所)および免疫治療の研究(千葉大学)、さらにはがんと栄養の研究、調査など、多岐にわたってがんとがん治療に関わってまいりました。
特に分子標的治療薬には多大な業績を残して参りましたが、これらの集大成として、1995年に、がんと長く共存する「がん休眠療法」を提唱し、特に抗がん剤治療においては、副作用を軽減し、長く継続できる方法を開発しました。
長年この方法を、高齢者や抗がん剤治療の副作用のため、標準治療が受けられない方に実践して参りました。
現在の抗がん剤治療は、多くの病院で標準治療至上主義となっており、標準的な抗がん剤治療が受けられなくなると、もう治療は何もないという状況になっています。
標準治療が終了したり、副作用などで標準治療が受けられない患者様に、次の治療を準備、提案することは、医師の責務であり、非常に重要な問題と考えております。
私は、そういった治療を「セカンドがん治療」と総称し、これまでの経歴を活かし、標準療法から外れてしまった患者様お一人お一人に、これまでの経過と現状をつぶさに相談、検討し、次の治療、つまり適したセカンドがん治療のご提案をさせて頂きたいと考えております。
業績要諦
がんの転移、特に血管新生の研究を行い、大腸癌の転移、増殖においてVEGFおよびそのレセプター2が重要な因子であることを世界で初めて明らかにした.これが、現在の抗VEGF抗体であるアバスチン治療およびサイラムザ治療につながった。
また、がん患者の延命には必ずしもがんの縮小は必要ない事を初めて示し、tumor dormancy therapy (がん休眠療法)を提唱した。これは、現在の抗癌剤の効果判定でSD、NC(不変)が有効になるきっかけとなった。
主な論文(被引用回数2022年4月現在)
- 1.Takahashi Y, et al: Expression of vascular endothelial growth factor and its receptor, KDR, correlates with vascularity, metastasis, and proliferation of human colon cancer. Cancer Res 55: 3964-3968, 1995. (1802回)
- 2.Takahashi Y, et al: Predicting recurrence in patients with node-ngative colon cancer: Prognostic value of vessel density and vascular endothelial growth factor expression. Arch Surg, 132: 541-546,1997. (437回)
- 3.Takahashi Y, et al: Platelet-derived endothelial cell growth factor in humancolon cancer angiogenesis: Role of infiltrating cells. J Natl Cancer Inst, 88: 1146-1151, 1996. (309回)
- 4.Takahashi Y, et al: Significance of vessel count, vascular endothelial growth factor, and its receptor (KDR) in intestinal-type gastric cancer. Clin Cancer Res, 2: 1679-1684, 1996. (329回)
- 5.Takahashi Y, et al: p53, vessel count, and vascular endothelial growth factor expression in human colon cancer. Int J Cancer 79: 34-38, 1998. (233回)
総被引用回数6600以上、h-index 33
がん休眠療法のご紹介
血液がんの休眠療法は行っておりません
休眠療法とは、がんの本質と抗がん剤の本質に基づき、抗がん剤治療の目的を従来の少しでも小さくすることから、少しでも長くがんが大きくなることを抑えることに変更するものです。つまり、がんと長く共存を目指すことを目標とします。具体的には、抗がん剤の量を、従来のヒトの限界量から人間として継続できる量に変更します。言わば、持続可能(サスティナブル)な抗がん剤治療です。
1.そもそも抗がん剤とはどんな薬か?
細胞は、分裂しながら増殖していますが、この分裂を種々の方法で阻害するのが抗がん剤です。そのため、分裂する細胞ならがん細胞だけではなくどんな細胞でも障害します。がん細胞を障害すれば効果と呼びますが、正常細胞(骨髄、毛髪、消化管粘膜)を障害すると副作用(白血球減少、脱毛、下痢、嘔吐など)と呼ぶにすぎないのです。つまり、抗がん剤とは、がんだけを障害する薬ではなく、がんを含む増殖している細胞すべてを障害する薬剤なのです。
2.なぜ、縮小ではなく、持続的な増殖抑制を目指すのか?
抗がん剤によるがんの縮小効果は、縮小したとしても多くの症例で半分程度にすぎません。この程度の縮小では、とても延命効果に繋がりません。これに対し、縮小しなくとも増殖抑制を継続できれば、より長い延命が得られることを私が示した論文が、アメリカ国立がんセンター機関誌に掲載されました。つまり、これまでのように副作用を犠牲にして、少しでもがんを小さくするために、ヒトの限界量を投与するのではなく、小さくならなくてもがんの増殖を抑え、副作用を軽微に抑え、それを長く継続すると言う、抗がん剤治療の新たな治療戦略を提唱するに至りました。
3.分子標的剤との共通点
2000年頃より、乳がんにおけるハーセプチンを初めとして、数多くの分子標的剤が開発されました。分子標的剤とは、がんの増殖や転移に関わる分子を特定し、これを抑える薬です。つまりは、がんを障害するよりむしろ、増殖を長く抑える薬剤です。休眠療法と全く同じ戦略です。実際、欧米の著名ながん研究者たちは、抗がん剤を低用量で投与することにより、がんの障害が難しくとも、ある種の分子を抑えることを示しました(メトロノミック療法)。
つまり、休眠療法と分子標的剤は、戦略が全く同じ治療であり、シナジー効果は高いと考えられます。
4.具体的な治療
抗がん剤を、副作用が軽微な程度しか出ない量を投与します。その代わりに、回数を多くします。
これにより、長くがんの増殖を抑制しつつ、がんのみならず副作用とも共存できる可能性があります。
また私が考案した方法は、抗がん剤の適量の個人差を考慮する方法です。アルコールで例えると、ほろ酔い加減になる量を一人ひとりで観察しながら、量を決める方法です。皆さんのアルコールの適量が互いに違いますように、抗がん剤でも個人差がかなり存在します。
がん休眠療法の学問的解説
私は、化学療法による延命は、縮小よりはむしろ増殖の抑制期間に大きく影響することを示し、”Survival without tumor shrinkage”なる概念を報告した ※1。また臨床試験のデータを解析し、50%以上の縮小率が得られ有効と判定された症例と、十分な縮小は得られないものの3ヶ月以上継続する「不変」と判定された症例とでは生存期間に差はないことを示した ※2。これらのことから、抗がん剤治療における「不変」を有効と判定すべきであること提案した。さらに、縮小よりもむしろ長期間の増殖抑制を目指す治療を、”tumor dormancy therapy”(邦名:がん休眠療法)と総称し、抗癌剤治療の戦略変更の必要性を提案した ※3。その後、欧米では乳癌における初めての分子標的治療としてHerceptinが開発されたが、この評価として著者の増殖抑制期間と同様のTime to Progression(TTP)と言う概念が使われた。その後、分子標的剤はもちろん、通常の化学療法の効果判定として、それまで唯一無二であった「縮小率」に加えてTTPが同時に使われるようになり、多くの臨床試験でTTPの延長が生存期間の延長に相関することから、ついに欧米では「不変」が有効と判定されるようになった。その後、本邦でも縮小がほとんど認められない抗癌剤で、NCが得られる率が高いことから延命につながった薬剤も開発された。
Tumor dormancy therapyの概念に合致した化学療法の方法については、種々の方法が考案された。特に、欧米からはFolkmanら血管新生の研究者を中心に、抗癌剤を低用量で頻回投与することにより、血管新生を抑制できることが報告された ※4。彼らはそれを”metronomic chemotherapy”と呼んだ。特に基礎分野では最も精力的に研究を進めたKerbelらは、血管新生が亢進する時に、血中内に上昇するcirculating endothelia precursor cells(CEP)なる物質を指標とした抗癌剤の濃度設定法を考案した ※5。また血管内皮細胞から作成されたHuvecと腫瘍に対する効果の差からの濃度設定法も発表した。臨床においては、私が現在のMTDから求められた標準量を、投与期間内で分割するMTD divided low dose法を考案した ※6。これは、時同じくして米国で開発されたweekly Paclitaxelとほぼ同様な治療法であった ※7。さらに、本邦で長く使用されてきた、経口の5-FU製剤やlow dose CDDPなどは、欧米の学者からは”metronomic chemotherapy”と同一と見做され注目された。
2001年11月、DNA螺旋構造の発見者で知られるWatson博士がCold Spring Harbor 研究所のThe Banbury Meeting(世界最高レベルの会議として知られいる。合宿形式で3泊4日で毎年開催)として主宰した”new concepts of cancer clinical trials”において、metronomic chemotherapyに関する研究者が一堂に会した。著者は、がん休眠療法の概念と、本邦で長く施行されてきた低用量化学療法を紹介した。特に、「手術で腫瘍を半分だけ切除しても、ほとんど人が馬鹿げた治療と言うのに対し、抗がん剤で腫瘍を半分にするとなぜ有効で素晴らしいとなるのか?」と言う問いかけには、Watson博士らに大受けであった。
著者は、抗癌剤のもう一つの大きな問題として、遺伝子薬理学的に見た量の個人差の重要性を指摘した。種々の分解酵素は遺伝子多型により異なり、それは抗癌剤の適量に直結する。国立がんセンターのグループでは、Docetaxelの個人差が3倍存在することを報告している ※8。著者は一定の量の抗癌剤治療ではなく、一定のAUCの抗癌剤治療を目指すべきとして、iMRD法を考案した ※9。毒性のグレード1もしくは2を指標として、投与量を決定するものであり、胃癌において全国的にrandomaized phase II試験がなされた。これは、MTDではない濃度設定法を用いた初めてのrandomaized phase IIであった。この試験により、有意の縮小率の改善を認めるとともに、酵素活性と抗がん剤の適量との関連性を示すことに成功した ※10。
※1.Takahashi Y and Nishioka K:J Natl Cancer Inst 87:1262-1263,1995.
※2.Takahashi Y, et all:Int J Oncol 17: 285-289,2000.
※3.高橋 豊著:Tumor Dormancy Therapy、医学書院、東京、2000.
※4.Browder T, Cancer Res 60: 1878-1886, 2000.
※5.Klement G, J Clin Invest 105: R15-R24, 2000.
※6.Takahshi Y, et al:Surg Today, 34:246-250,2004.
※7.Seidman AD, et al: J Clin Oncol 16: 3553-3361,1998.
※8.Yamamoto N, et al:J Clin Oncol 20: 1601-1609,2006.
※9.Takahashi Y, et al: Pancreas 30: 206-210,2005.
※10.Komatsu Y, et al:Antica Drug 22:576-583,2011.
参考図書
高橋 豊著:今あるがんを眠らせておく治療、主婦の友社、2010刊
高橋 豊著:がん休眠療法、講談社、2000刊
主なマスメディア紹介
- NHK ためしてガッテン 2002
- テレビ東京WBS 2002
- テレビ朝日スーパJチャンネル 2003
- 日経新聞 2001,2003,2004
- 朝日新聞科学欄「直言」2003
- 読売新聞「医療ルネサンス」2006